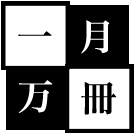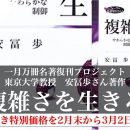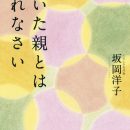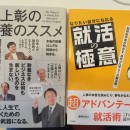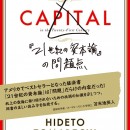2016.05.01 SUN - 読書ブログ
家族問題『毒親の子どもたちへ』斎藤学 毒親から解き放たれるために
Warning: Undefined array key "adf" in /home/blancell/demospace.page/public_html/readman-wp/wp-content/plugins/rejected-wp-keyword-link-rejected/wp_similarity.php on line 41
Warning: Undefined array key "sim_pages" in /home/blancell/demospace.page/public_html/readman-wp/wp-content/plugins/rejected-wp-keyword-link-rejected/wp_similarity.php on line 42
 記事を読んでいただきありがとうございます。一月万冊の大下周平です。
記事を読んでいただきありがとうございます。一月万冊の大下周平です。今回取り上げるのは『毒親の子どもたちへ』という斎藤学さんの本です。毒親というと基本的には子供の自尊心を奪い、親自身のトラウマやコンプレックスを子供を介して克服しようとしているような状態の親です。その介入の仕方は実に様々で、この本の中では4つのタイプが取り上げられています。過干渉、統制型の親という最も訴えの多いタイプ、無視親といういわゆるネグレクトのような子供に全く目を向けない放任タイプ、ケダモノのような性的虐待や殴ったり蹴るなどの暴行を加えたり、罵声を浴びせたり生命の危機を覚えるような暴力を振るうタイプ、自らが精神障害を持った病気の親というタイプの全部で4つです。これら4つのうち、それぞれの特性を併せ持つ親ももちろんいるでしょうし、これらのタイプではない新しいタイプの親もいるかもしれません。ですが、いずれにせよ言えることは子供の自尊心を奪い、親がいないと子供の存在自信が成立しないように仕向けることが毒親として共通して行うことです。
 過去に私も言葉の暴力や実際に殴ったり蹴ったりという経験が子供の頃にあったことはゼロではありません。むしろ幼少期は自分では覚えていませんが父親がすぐに手をあげる人であったため、母親がそれを諌め育児にかかわらなくていいと宣言したと聞いています。そして姉に聞くと父親の手が怖かったと言っていました。それは幼少の頃に振るわれた暴力による恐怖心がずっと潜在意識に残っているからでしょう。私も少なからず叱られたりして手を出されたことはありますが、父親の手が怖いというほどではなかったので、最初の子供である姉の時は父親が育児に関わる時間や場面も多かったのかもしれません。そのときの対応を見て母親が育児にかかわらせないようにしたので、私自身にはそういった恐怖に対する記憶がないのかもと思います。とはいえ、やはりある程度決められた時間にお風呂に入らないと怒られたりすることはありましたし、基本的に短気な方なのでカッとなって怒鳴られることはままありました。だからいうことを聞かないと怒られる、怖いという感覚は今でも覚えています。
過去に私も言葉の暴力や実際に殴ったり蹴ったりという経験が子供の頃にあったことはゼロではありません。むしろ幼少期は自分では覚えていませんが父親がすぐに手をあげる人であったため、母親がそれを諌め育児にかかわらなくていいと宣言したと聞いています。そして姉に聞くと父親の手が怖かったと言っていました。それは幼少の頃に振るわれた暴力による恐怖心がずっと潜在意識に残っているからでしょう。私も少なからず叱られたりして手を出されたことはありますが、父親の手が怖いというほどではなかったので、最初の子供である姉の時は父親が育児に関わる時間や場面も多かったのかもしれません。そのときの対応を見て母親が育児にかかわらせないようにしたので、私自身にはそういった恐怖に対する記憶がないのかもと思います。とはいえ、やはりある程度決められた時間にお風呂に入らないと怒られたりすることはありましたし、基本的に短気な方なのでカッとなって怒鳴られることはままありました。だからいうことを聞かないと怒られる、怖いという感覚は今でも覚えています。どんな親にせよ結局のところほとんどの家庭において毒親は発生しているのではないかと思います。私自身こういった本を読まなかったら親のことを尊敬する両親として間違いなく信じていたでしょうし、それを否定されようものなら一気に気分が悪くなって話をする気が失せてしまうと思います。前回取り上げた本もさることながら親と子供の関係性に関する本を読むと、そういった私自身の過去の思い出も、過去付き合ってきた恋人や友達が経験してきた家庭内のことも、だいたい本に似たような事例として掲載されていました。ここが一番の驚きであり、盲点でした。なぜならそういった家庭内における事件は特別な話として滅多にない話としてあるものだと思っていましたし、毒親ではない家庭の方が多くて、一部の家庭において毒親と言われるような、子供にひどいことをする親が存在すると誤解していました。それこそが大きな誤りでした。どこにでも毒親がいますし、今も増え続け、そして毒親をどく親と思わないまま成長していく子供達がいるのです。
本書のあとがきにはこう書かれています。
「毒親の子どもたちというのは、自身を健全だと思って毎日を過ごしている人たちを含めたすべての人です。この本がみなさんのお役に立てるよう願っています。」
要するにすべての子どもたちが毒親の子どもたちであり、すべての子どもたちの親が毒親であると言っています。これはとても受け入れがたいと思う人が相当数いると思います。私も過去そう言われれば断固として否定したでしょう。でも色々と似たようなテーマで書かれた本を読み進めて行くうちに当たり前のことなんだなと気づかされます。どこまでいろんな本を読み進めても、やっぱり毒親であることは否めないし、何も知らないまま知識を増やさずただ理想の家族像を追い求めて結婚し、子供を作っていたら間違いなく私自身が毒親となっていたでしょう。それだけ根深い問題だと思います。それと同時に根深いけれども解決できる問題でもあります。
 理想の家族像とは一体なんでしょうか?私は親を見て育ち、ある一定の年齢になったら結婚して子供を作り、家を購入して仕事を頑張り、そして孫に囲まれて老後を過ごすということを実に当たり前のこととして考え、そのためにどうすればいいのかを無意識的に実行していたと思います。それは誰によってそう思い込まされていたのでしょうか。理想の家族とは存在するのでしょうか。そしてそれはどのように定義されるのでしょうか。すべては空想であり妄想です。私が心から望んだものでもなく、社会や家族、地域や親戚関係が醸成する空気の中にそれは存在し、そして誰しもがそれを実現できていません。理想の家族なんてはなから存在しないのです。ないものを追い求めて、ないことで苦しみ、ないにもかかわらずどこかにあると信じさせられて毎日を過ごす。とても滑稽でもったいない人生です。
理想の家族像とは一体なんでしょうか?私は親を見て育ち、ある一定の年齢になったら結婚して子供を作り、家を購入して仕事を頑張り、そして孫に囲まれて老後を過ごすということを実に当たり前のこととして考え、そのためにどうすればいいのかを無意識的に実行していたと思います。それは誰によってそう思い込まされていたのでしょうか。理想の家族とは存在するのでしょうか。そしてそれはどのように定義されるのでしょうか。すべては空想であり妄想です。私が心から望んだものでもなく、社会や家族、地域や親戚関係が醸成する空気の中にそれは存在し、そして誰しもがそれを実現できていません。理想の家族なんてはなから存在しないのです。ないものを追い求めて、ないことで苦しみ、ないにもかかわらずどこかにあると信じさせられて毎日を過ごす。とても滑稽でもったいない人生です。人生の主人公は私であり、この記事を読んでいるあなた自身です。それぞれの人生はそれぞれが責任を取ることが当たり前であり、他の誰しも変わってくれません。だったらそんな理想の家族像とか、親の期待とか、そんな無意味なものに振り回されるのではなく、自分自身が人生をどのように過ごしていきたいのかに時間と脳みそを費やしましょう。誰のものでもない自分自身の人生なのですから。それこそが毒親から解き放たれるための唯一無二の秘策だと私は思います。
Warning: Undefined array key "adf" in /home/blancell/demospace.page/public_html/readman-wp/wp-content/plugins/rejected-wp-keyword-link-rejected/wp_similarity.php on line 41
Warning: Undefined array key "sim_pages" in /home/blancell/demospace.page/public_html/readman-wp/wp-content/plugins/rejected-wp-keyword-link-rejected/wp_similarity.php on line 42
大下 周平
一月万冊の清水と大学時代からの友人。ゲームが好き。清水にはじめて『こいつには絶対格ゲーで勝てない・・・!』と悔しがらせた男。彼と代表が対戦して勝てる可能性は5%以下。月に100〜300冊ほど読書をし、清水の会社で執行役員としても活躍!
新着記事
-
2020.03.04 WED
-
2020.02.24 MON
人気ランキング
-
2016.05.05 THU
-
2016.05.22 SUN
-
2017.07.18 TUE
-
2014.04.10 THU
-
2014.12.10 WED
Warning: Undefined variable $x in /home/blancell/demospace.page/public_html/readman-wp/wp-content/themes/readman2017/sidebar.php on line 97